双葉郡広野町は、福島県浜通り地域にある双葉郡の最も南に位置し、太平洋と里山に挟まれた自然豊かなエリアです。「東北に春を告げるまち」と称され、温暖な気候に恵まれています。JR常磐線「広野駅」から歩いて15分ほどの太平洋を望む小高い丘に建つ「福島県立ふたば未来学園」は、街路をイメージさせるような開放的なつくりで、その近隣にはこども園や児童館などの教育環境が整っています。
2011年3月11日、国内観測史上最大規模の『東日本大震災』が発生。この地震により東北地方の太平洋沿岸地域は広範囲に津波に襲われ、双葉郡も甚大な被害を受けました。また、東京電力の福島第一原子力発電所の事故により、避難を行った自治体のひとつでもありました。
この地域の復興のシンボルでもある「福島県立ふたば未来学園」は、2015年には文部科学省の「スーパーグローバルハイスクール(SGH)」に、続いて2020年には「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」の指定校になりました。その一貫したテーマは「原子力災害からの復興を果たし、新たな地域社会を創造するグローバルリーダーの育成」です。2024年には新たに「ワールド・ワイド・ラーニング(WWL)コンソーシアム構築支援事業」の拠点校となり、地域のコミュニティを支え、世界から地域を活性化するためのグローバルな人材の育成を継続しています。
震災から14年、「ふたば未来学園」創設の背景や、子どもたちの学校生活の様子など、福島県立ふたば未来学園副校長の對馬俊晴氏と、探究教育の発展に尽力されている企画研究開発部副主任・教諭の齋藤夏菜子氏にお話を伺いました。

福島県立ふたば未来学園
副校長 對馬俊晴氏(写真右)
企画研究開発部 副主任・教諭 齋藤夏菜子氏(写真左)
地域が支えた子どもたちの学びの場

――「ふたば未来学園」は、高校は創設から10年、中学校は6年目を迎えられました。震災後、子どもたちの学びをどのように創っていったのかお聞かせください。
- 對馬
- 東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故により、双葉郡のほとんどの住民が県内外への避難を余儀なくされました。双葉郡には八つの町と村があり、そこに五つの県立高校の校舎がありましたが、全ての学校が休校になりました。避難した家族の子どもはそれぞれ違う土地で色々な学校に転学をしますが、自分たちの生まれ育った場所、両親、おじいちゃんやおばあちゃんがいる故郷の学校とは違う。帰還を望んでも、子どもを通わせる学校が無い土地に戻るのはなかなか難しい。彼らの心の支えとなる双葉郡に、やはり学校がほしい。
そこでこの課題に8町村の教育長が集まり、子どもたちの学びの場をどう保障するか、どう確保していくかと協議会を立ち上げ、2013年「福島県双葉郡教育復興ビジョン」をとりまとめました。どんな困難も乗りこえ、未来を生きる強さを持つ人材を育てようという方策の中に、県立中高一貫校の設置がありました。そこで広野町にもともとあった県立高校の機能を再建し、「ふたば未来学園」を創建させました。高校は震災4年後の2015年、中学校は2019年の開校です。
改革では足りない、「変革」でなければならない
――ふたば未来学園の建学の精神「変革者たれ」の校訓についてお聞かせください。
- 對馬
 「変革者たれ」とは、震災経験を糧に、復興をかなえる人材を育てることを目標にした建学の精神です。生徒たちの学びをどうやって保障するか考えた時、これから求められる学びはどうあるべきか問われました。これからの世の中を形成していく人材を育成すること、東日本大震災と原発事故という、人類が今まで経験したことが無い苦難を背負ってしまった双葉郡に学校をつくることは「変革」であり、自分たちで新しい社会をつくっていこうという大きな使命です。現実社会で実際に起こっている困難を間近で体験しながら、それをどう解決していくのかに「改革」では弱い、「変革」でなければならない。自分自身を変革し、地域をより良く変革し、社会を変革していくという学びが重要だと考え、建学の精神として「変革者たれ」としました。
「変革者たれ」とは、震災経験を糧に、復興をかなえる人材を育てることを目標にした建学の精神です。生徒たちの学びをどうやって保障するか考えた時、これから求められる学びはどうあるべきか問われました。これからの世の中を形成していく人材を育成すること、東日本大震災と原発事故という、人類が今まで経験したことが無い苦難を背負ってしまった双葉郡に学校をつくることは「変革」であり、自分たちで新しい社会をつくっていこうという大きな使命です。現実社会で実際に起こっている困難を間近で体験しながら、それをどう解決していくのかに「改革」では弱い、「変革」でなければならない。自分自身を変革し、地域をより良く変革し、社会を変革していくという学びが重要だと考え、建学の精神として「変革者たれ」としました。
生徒たちが取り組む地域課題解決型プロジェクト学習「未来創造探究」
――ふたば未来学園が地域と共に展開している「未来創造探究」はどのような学びですか。
- 對馬
- 「未来創造探究」は、生徒たち自身で地域に課題を見つけ出し、地域の方や各分野で活躍している方のアドバイスをもらいながら実践し、地域再生につなげていこうという学びです。開校から10年継続しているこの学習に生徒たちはたいへん意欲的に取り組み、個人・グループ、中学校から高校まであわせると、現在は学校全体で300プロジェクトほどが実践されています。
――具体的にはどのような学習ですか。
- 齋藤
 中学校では身近な課題に焦点をあて、生徒たちの考えを発表しながら合意形成を育み、みんなで協動し議論しあい、ひとつのものをつくる力を身につけていきます。外部講師が教える哲学対話の授業では、自分とは違う意見を持つ人を否定するのではなく、興味を持ち、その違いをおもしろがるという感性を育みます。
中学校では身近な課題に焦点をあて、生徒たちの考えを発表しながら合意形成を育み、みんなで協動し議論しあい、ひとつのものをつくる力を身につけていきます。外部講師が教える哲学対話の授業では、自分とは違う意見を持つ人を否定するのではなく、興味を持ち、その違いをおもしろがるという感性を育みます。
高校に上がると実際の地域課題に向き合います。受験で多地域から入学してくる子どもも多いので、震災時の地域の状況や、どんなことがあったのかをみんなで見に行きます。そこで初めてこの地域の現在の様子を知り、暮らしている方々との関わりを持ちはじめます。
――探究の学習では、海外の地域と交わる取り組みもあるそうですね。
- 齋藤
- 一部の生徒は、自分たちの探究したプロジェクトを発表するため、ドイツやニューヨークへ海外研修に行きます。英語でコミュニケーションし、現地の方からフィードバックをもらい、グローバルな視点からも地域課題を解決する力をつけます。
- 對馬
- アメリカやドイツなど世界に目を向けると、自分たちの地域で起こっている対立、葛藤、困難がもっと大きなレベルで、同じような構造を持って起きているということを発見します。それらは相似形になっていて、生徒たちが感じる地域課題と同じような上手くいかないものごとは、実は教室の中にもあり、家庭の中にもある。海外研修で得たそれらのヒントや意見を持ち帰り、類似する構造を比較し、あるいはそこから新たな視点を得て、その解釈を自分たちの地域に反映させます。
地域課題を演劇で表現

――芸術の必修教科に、「美術」や「音楽」と並んで、新たに「演劇」を設定されたそうですね。福島をフィールドとした地域課題を「演劇」で表現する学習の取り組みについてお聞かせください。
- 齋藤
- 演劇で表現する目的は、ものごとを多面的にとらえる力を身につけることです。地域の課題として、意見が対立する場面を描くとき、その人たちはなぜ対立する意見を持つのか、それぞれの立場や背景はどうなのか、とさまざまな角度から想像して考えます。また、探究に必要な論理的思考力と批判的思考力も育みます。探究というのは課題を研究するのではなく、人間と、その人間がつくる社会について探究していくものです。論理的に考えるとは、演劇をつくること自体が論理的に情報を出していかないと観客側には伝わらない。また、批判的に考えるというのは、例えば、福島や世界で起きている物事について、「大人はこう言っているけど本当かな?」というアンテナを持ち、自分からもっと深掘りしていくということです。そのことこそが演劇をつくる意味だと思います。
――演劇で表現する効果はありますか。
- 對馬
- 開校当時から演劇教育を間近に見てきて、この教育的効果は非常に高いと感じています。演劇は教科学習の要素が全て入っていながら、言葉になりにくいもの、絵になりにくいものを空間的、時間的に表現することができます。演じる側の学びも素晴らしいですが、観る側も色々なことを感じます。そこで感じたことを自分の生き方に照らし合わせ、自分の人生にあてはめながら想像することは子どもたちの大きな学びにつながります。ものごとには色々な背景があり、様々な立場の人がいて、それぞれのタイミングがあり多種多様なことが混ざり合っています。これらを相対的に、あるいは全体でとらえることは、他の教科ではできない学びだと実感しています。
- 齋藤
- 演劇をつくることは大変な作業です。誰もがはじめからできるものではなく、中学生の時から積み重ねる探究の学習が血となり肉となり表現につながります。最後の発表会で自分たちがインタビューした方々に演劇を観てもらい、フィードバックをもらうことで地域の役に立てたと実感する、これはたいへん意味のある学びだと思います。

演劇の授業の様子
グループごとにテーマを決め、打ち合わせを重ね、発表を行う
校舎内にある本格的なシアターや多目的スペース

――演劇の発表が行われる「みらいシアター」は本格的なホールですね、どのような活用がされていますか。
- 齋藤
- 校舎の1階にある「みらいシアター」は、照明や音響などのスタジオ機材が整っている本格的なホールです。教科学習である表現コミュニケーション授業や演劇授業では、定期的にお呼びするプロの劇作家や演出家の方から本格的な指導を受けています。探究授業では、スクリーンにスライドを投影し、演台を置いてマイクで発表するのですが、その環境にも生徒たちはやりがいを感じている様子が見てとれます。私は演劇部の顧問をしているのですが、演劇部は役者だけではなく裏方を希望し入部してくる生徒もいるので、実際のシアターと同じように照明機材や移動観覧席の操作ができることに、生徒たちのモチベーションはとても高いです。
――「移動観覧席」収納時の活用はいかがですか。
- 齋藤
 観覧席を収納するとシアターは大変広い空間になるので、小規模な体育館のようにも使用できます。体育の授業で創作ダンスをすることもありますし、床に直に座って学年集会なども行っています。
観覧席を収納するとシアターは大変広い空間になるので、小規模な体育館のようにも使用できます。体育の授業で創作ダンスをすることもありますし、床に直に座って学年集会なども行っています。
――実用性はいかがですか。
- 齋藤
- 移動観覧席の利用は授業や部活動に定着していて、座り心地の良い観覧席は生徒たちに好評です。探究授業をシアターで行うと言うと喜びますし、座席に座りたがります。シアターは地域や外部の方も利用する機会が多くあり、頻繁に観覧席の出し入れをしていますが、便利で、しかも丈夫です。
――みらいシアターの隣にある多目的スペース「双葉未来ラボ」とは。
- 對馬
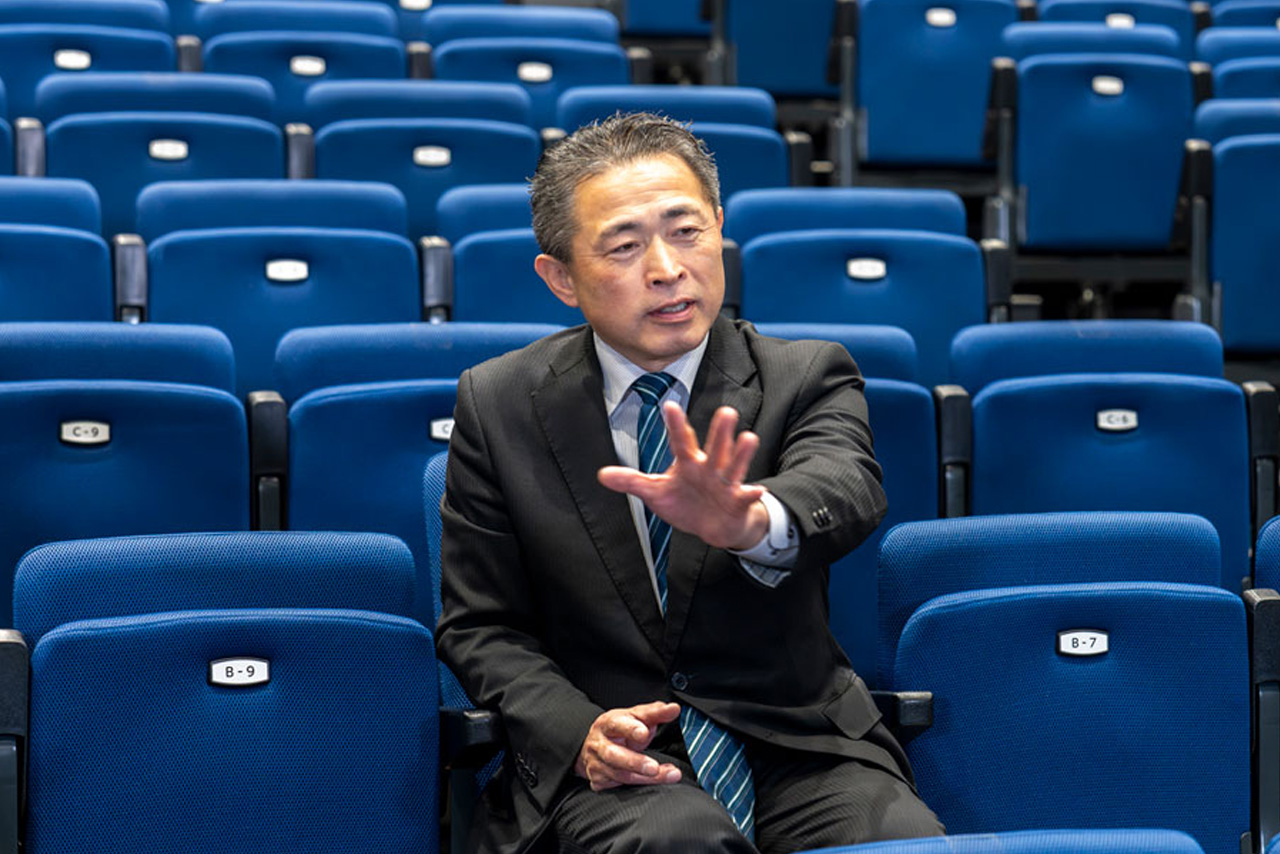 「双葉みらいラボ」は、生徒がリラックスしたりコミュニケーションを広げたりする学校の中心地で、部活動である社会企業部が運営するカフェもあります。放課後の時間は、双葉みらいラボの運営に携わるNPO法人カタリバのスタッフに、生徒たちが青春の悩みを聞いてもらったり、探究の学習をサポートしてもらったりと「ナナメの関係」をつくっています。さまざまな活動がここを中心に行われ、地域にも開かれた多種多様な交流のスペースとなっています。
「双葉みらいラボ」は、生徒がリラックスしたりコミュニケーションを広げたりする学校の中心地で、部活動である社会企業部が運営するカフェもあります。放課後の時間は、双葉みらいラボの運営に携わるNPO法人カタリバのスタッフに、生徒たちが青春の悩みを聞いてもらったり、探究の学習をサポートしてもらったりと「ナナメの関係」をつくっています。さまざまな活動がここを中心に行われ、地域にも開かれた多種多様な交流のスペースとなっています。
- 齋藤
- 放課後のラボはたいへんに賑やかです。子どもたちと年齢が近いカタリバのスタッフに、勉強を教えてもらったり、おしゃべりをして過ごしたりしている生徒たちの様子が見られます。ナナメの関係から生徒の悩みを引き出してくれることもあるので、双葉みらいラボは生徒と教師のコミュニケーションの架け橋にもなっています。

双葉未来ラボ
地域での実践を踏み台に、社会に飛び立つグローバルリーダー
――「ふたば未来学園」の子どもたちの未来は。
- 齋藤
- 自分たちの学校がどんなに恵まれた環境だったか、どんなに素晴らしい学びだったかに気がつくのは、生徒たちが卒業し、それぞれ違う世界に入った時だと思います。社会に出てからも、探究の授業で実践したことを思い出し、自分でアクションを起こし、世の中を変えて行けるような大人になってほしいですね。たくさんの方から教わって得た学びを社会に還元して、活躍してほしいと願います。
- 對馬
- 本校の教育の大きな特徴として、「出会い」があると思います。地域や背景が異なる生徒、自分とは違う力を持った生徒、個性豊かな教職員、外部講師の先生、地域の方、各分野の専門家、関わりを持った世界の方々、これら「様々な出会い」の中で、一緒に学び発展していきます。ここで学び実践を積んだ生徒たちが、10年後、20年後、30年後に振り返った時、あの出会いがあって良かった、あの出会いが今に繋がっていると、それぞれの人生の強みになることを願います。
――発展しつづける「ふたば未来学園」の学びは、子どもたちを実社会のリーダーに導くすばらしい教育だと感じました。大きな困難を乗りこえた学校だからこそ、未来に伝える内容も深い教育なのだと思います。本日はどうもありがとうございました。

「ふたば未来学園」のインタビューを終えて
私が学校を取材させていただいた日、シアターでは高校3年次生のクラスが、プロの演出家による表現コミュニケーションの演劇授業をしていました。発表日だったようで、グループに分かれた生徒たちが順番にステージで演じます。テーマは友だち同士の「いじめ」や、「SNS」の間違った使用で人を傷つけてしまう、「給料」格差の問題や「LGBTQ」課題、「環境破壊」問題という内容でした。難しいテーマを、それぞれ5分ほどの芝居で瑞々しく丁寧に演じる生徒たちの姿に、大人である私は何か大きなものを問われました。新たな学びを実践する若者たちの今後が楽しみです。
取材日:2025年1月
動画
#福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 #みらいシアター #双葉未来ラボ #スーパーグローバルハイスクール #SGH #地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型) #ワールド・ワイド・ラーニング(WWL)コンソーシアム構築支援事業 #未来創造探究 #移動観覧席