岡山県の北東部、那岐山の麓に位置する奈義町は、2002年に住民投票により合併しない単独町政を選択しました。単独町制維持のために人口減少を最重要課題として捉え、定住促進のための様々な施策を実施。2012年には「奈義町子育て応援宣言」を行い、移住や子育ての支援策を充実させることで、2019年には全国トップクラスの合計特殊出生率2.95を記録。少子化対策の“奇跡の町”として注目されています。また、奈義町はアートの面でも知られており、特に1994年に建設された「奈義町現代美術館」は世界的な建築家・磯崎新氏が設計した体感型美術館の先駆けといわれています。
奈義町文化センターは町民の生活・文化向上のための中心施設で、生涯学習を推進するための充実した設備が整っています。しかし築年数が経過していたこともあり、幅広い世代の方々がより快適に過ごせる空間を目指し、2024年にイスの入替えをメインに大ホールの改修を行いました。今回のインタビューでは奈義町長の奥正親氏に、改修の目的をはじめ、魅力あるまちづくりに欠かせない文化・アートの役割など、貴重なお話を伺いました。

奈義町長
奥 正親 氏
より快適な空間を目指し、イスの入替えを実施

――今回の改修の目的について教えてください。
奈義町文化センターは1985年に建設され、集会室、和室、視聴覚室、調理室、作業棟、稽古場など多くの施設があり、町民の生涯学習施設として機能しています。大ホールは小さな補修をしながら長年利用してきましたが、2025年2月に町制施行70周年の記念式典を予定していたこともあり、今回大規模な改修を実施しました。
――どのような改修を行ったのでしょうか。

以前の客席は490席あり、満席になると隣との間隔が窮屈な印象だったため、ゆったり座っていただけるイスへ入れ替えました。町の人口も、建設当時の約8,000人から約5,500人へと少し減少しているので、座席数を減らして一席ごとの幅を広げ、368席にしています。改修内容については、音響や照明、空調など色々と要望はありましたが、まずは利用する町民に一番喜んでいただけるイスを優先しました。
そのほかには、床シートの貼替えと壁の塗替えを行いました。特に床は長年の使用で黒ずんできていましたが、貼り替えたことで館内がかなり明るくなりましたね。また車イスで舞台に上がれるようにスロープを作り、照明のLED化も行っています。
(写真:改修前のホール)
――大ホールの改修には奥町長も思い入れがあったのでしょうか。
私は元奈義町の職員で、文化センターにも長年勤務していましたから、イスのことは気になっていました。
ここは高齢者の方も多く利用されていて、色々鑑賞するのは楽しいけれどイスが狭くてちょっと隣が気になるというお話は聞いていました。それではせっかくの舞台も心から楽しめないので、隣の方とも気持ちよく話ができるようなゆったりした客席にしたいとは前々から考えていました。
――今回コトブキシーティングのイスを導入していただきましたが、どのような点がポイントになりましたか。
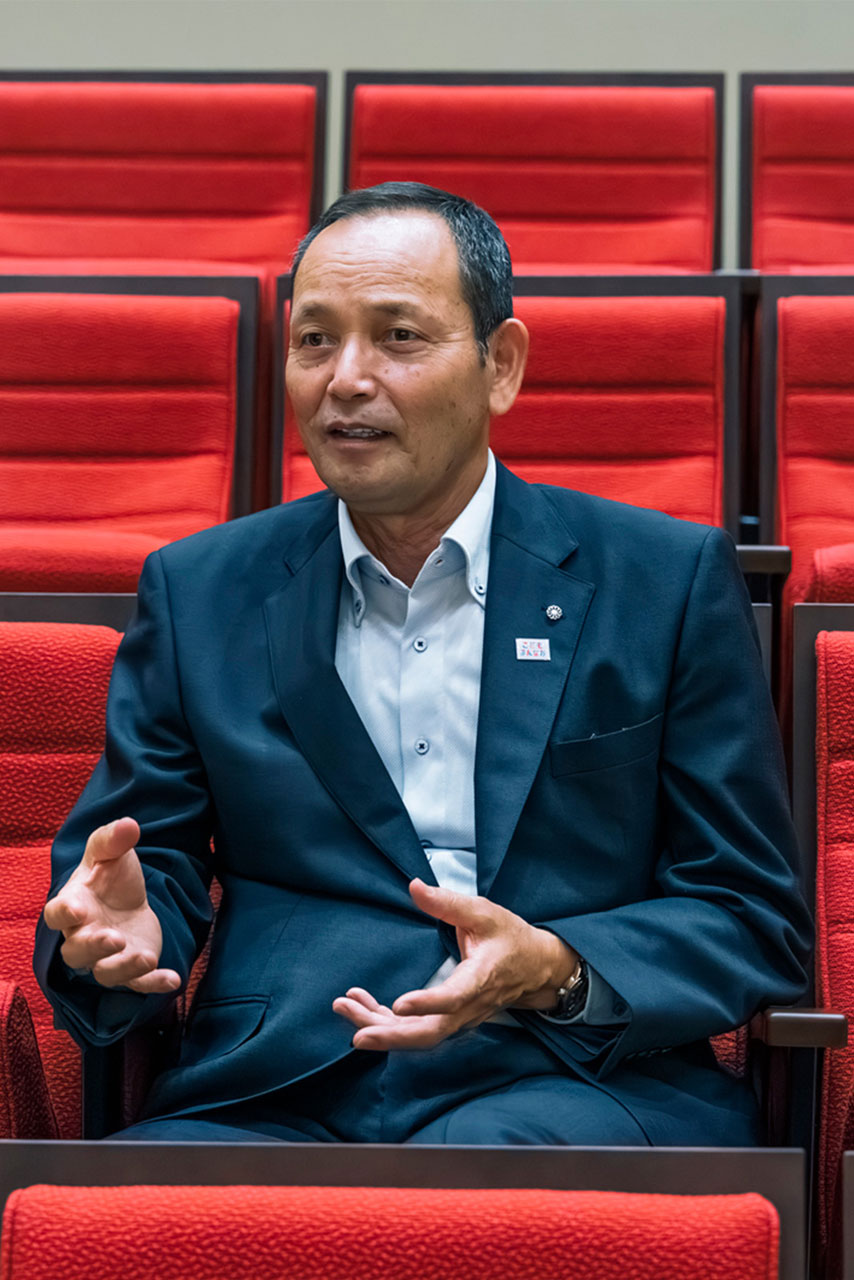
サンプルを文化センターのロビーにも置いて、職員や町民にも実際に座っていただき、最終的に御社のイスが選ばれました。
今回の一番の目的はイスの幅を広くすることでしたが、座り心地についても重視しています。御社のイスになった理由は、一つは座の先端部分が細くなっていることです。座っているときにも足を動かす余裕があり、足を引きやすいので立ち上がるのが楽ですよね。もう一つは座ったときのホールド感です。
――ありがとうございます。今回導入していただいた「ダックテールシート®」の「スペーシア」タイプは、おっしゃるように立ち上がりやすく、高齢者の方にも人気があります。また座面後方を持ち上げた形状が腰への負担を軽減するので、実際に座ることで快適さが実感いただけたと思います。
ほかにもポイントはありましたか。
色ですね。前のイスがエンジ系の色だったので、以前と同じような色合いで少し明るい色を選びました。違う色合いにする意見もありましたが、町民が長年親しんできた雰囲気とあまり変わらないことを重視しました。

ダックテールシート
®:座の先端は細く、座面後方を持ち上げた形状で腰への負担を軽減する
――今回の改修工事には過疎債を利用し、イスについては分離発注を採用していますね。
町の負担をいかに少なく良い製品を導入するかということで、財源確保のための様々な方法を検討しました。今回利用した過疎対策事業債は、返済に対する国の補助率が大きいので、過疎地域に指定されている奈義町にとって有利な地方債ということで活用しました。またイスの分離発注は職員からの提案です。大ホール全体の改修工事と分離してイスを備品として購入することで、諸経費が約2割程度は減っています。
文化芸術活動の中心拠点となる文化ホール
――大ホールの改修は2024年9月に開催された「森の芸術祭 晴れの国・岡山」のイベントに間に合わせるために、急いで工事が進められたそうですね。

岡山県北12市町村を会場に開催された「森の芸術祭 晴れの国・岡山」の中で、奈義町では俳優やダンサーとして活動する森山未來さんが奈義町主催のイベント「ART de MEAT Nagi 2024」と「奈義町農林業祭」とコラボレーションした「さんぶたろう祭り」を企画し、芸術祭のオープニングを飾りました。奈義町には江戸時代から伝わる伝統芸能で、岡山県重要無形民族文化財にもなっている横仙歌舞伎(よこぜんかぶき)があるのですが、その横仙歌舞伎をヒントにした新作パフォーマンスも森山さんが披露してくださいました。
その会場となったのが奈義町現代美術館前の奈義町シンボルロードで、雨が降ると屋外では上演できないため、雨天の場合の会場をどうしても確保しておきたかったのです。実際には屋外で上演できたので、大ホールでは映像作品「IKI NO KOE」を上映しました。映像作家の宮尾昇陽さんが制作した奈義町の子育ての魅力を伝えるドキュメンタリーフィルムで、後に令和7年度の全国広報コンクール映像の部で「入選」に選ばれています。
――本来、大ホールはどのような内容で使われているのですか。

基本的には町主催の町民が参加するイベントが中心です。もちろん、学校行事でも使っています。
奈義町には子供から高齢者まで自由に学べる生涯学習教室があり、現在、芸能部・文化部合わせて30の団体が自主的に活動しています。中には横仙歌舞伎や奈義民舞の保存会もあり、趣味を楽しむと同時に伝承文化の保存活動にもつながっています。また、保存会が指導するこども歌舞伎教室、こども太鼓教室などの子供向けの活動や、生涯学習課が主催する「奈義町長寿大学」なども開催されており、これらの活動はすべて文化センターが拠点になっています。
(写真:横仙歌舞伎大公演の様子)
――文化センターが町民の様々な文化芸術活動の中心であり、そのメインの発表の場が大ホールなのですね。
そのとおりです。企画・運営を行う生涯学習課の事務所も文化センター内にあるので、利用者からの生の声を聞きながら活動しています。
改修後、最初に行われた町民主体のイベントは、通称“町の文化祭”と呼んでいる奈義町生涯学習フェスティバルです。このイベントは、町民が生涯学習活動を通して制作した絵や書、また園児や小中学生の図画工作などを施設全体で展示します。大ホールでは、20の団体による踊りや演奏などの舞台発表も行われました。毎年11月に開催しているのですが、今年は新しくなった大ホールの町民へのお披露目を兼ねたイベントとなりました。
また2025年2月には、地区コミュニティの活性化を図る目的で町内の各世帯から多彩な作品を出展してもらう「奈義町傑作展」も開催しました。出展者数約470人、出展数は約800点に及び、文化ホール全体を使って展示・発表しています。
――外部の方を招くイベントもありますか。

もちろんあります。地方に住んでいても、都会と同じように本物を見る機会を提供したいと考えており、プロによるイベントも企画しています。
例えばすでに2回来ていただいているズーラシアンブラスは、希少動物のかぶり物をして演奏するパフォーマンスが子供から大人まで人気があります。1回目は小中学校の芸術鑑賞、2回目は町制70周年を記念した「音楽の絵本 オールスターズ ズーラシアンブラス演奏会」として開催しました。
(写真:奈義町町制施行70周年記念式典の様子)
――新しくなったことで、大ホールの稼働率や利用の仕方に変化はありますか。
稼働率や利用内容は基本的には改修前と変わっていませんが、新しいイスはとても評価が高いです。 席数を減らしたことに関しても、現在の人口に対して適正規模になり、むしろ使いやすくなったようです。
(左から)倉敷管弦楽団奈義町公演、ファミリーコンサート、インド映画マサラ上映会の様子
すべての世代に魅力あるまちづくりを目指して
――奈義町は2012年に「子育て応援宣言」を行い、様々な支援施策を実施していますね。
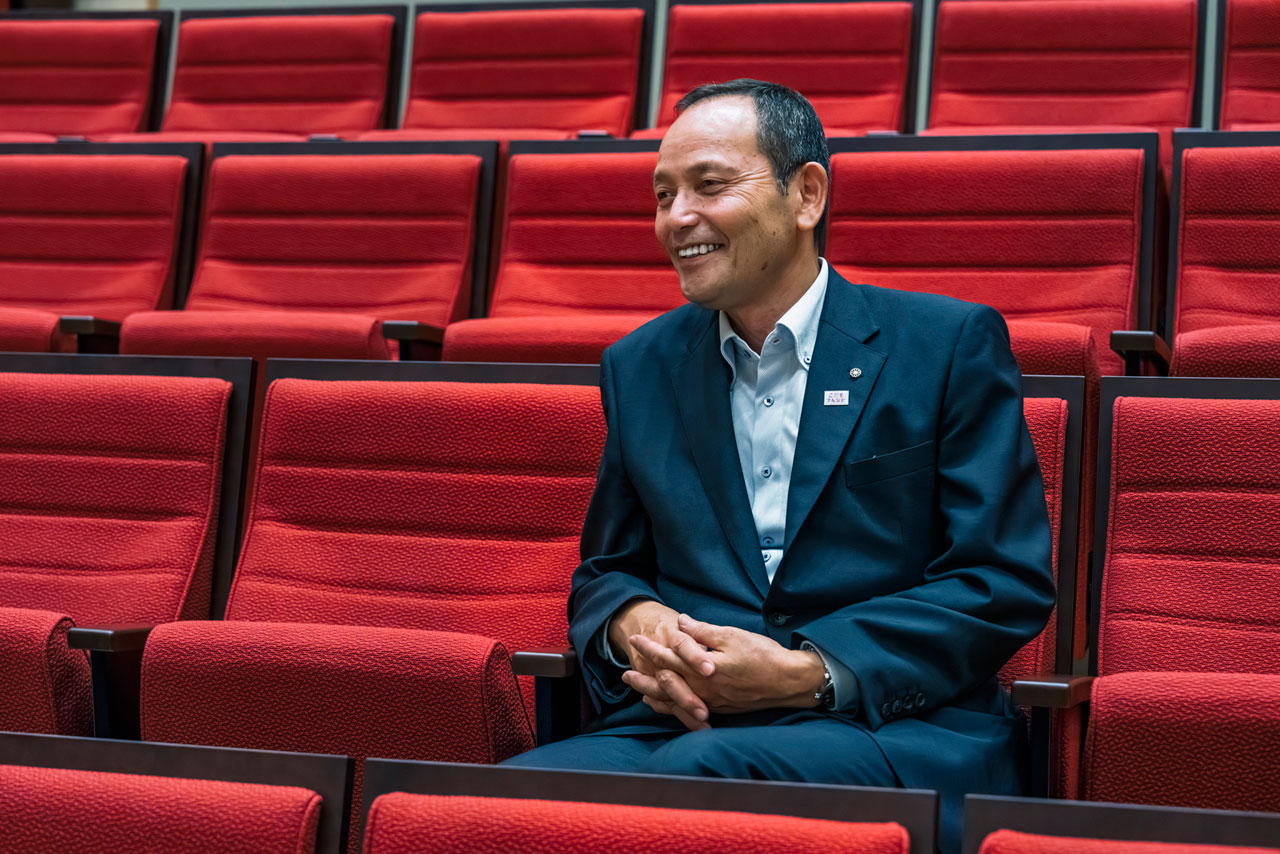
奈義町では人口減少に対応するために、子育て支援と教育、そして高齢者支援とのバランスを取りながら、すべての人が暮らしやすいまちづくりに取り組んでいます。若い人が町にいて子供がいる、そして若い人が高齢者を支える、こういう循環を起こしたいと考えています。そのためには若い人が魅力を感じる、住んでみたいと思うような要素が必要であり、子育て支援や教育、医療は基礎的なものとして欠かせません。
子育て・教育支援策としては、基本的には二通り行っています。一つが経済的な支援で、医療費の無料化や教材費・給食費の無償化、高等学校等就学支援などです。もう一つは精神的な支援です。奈義町子育て等支援施設「なぎチャイルドホーム」は、地域ぐるみで子育てを支える拠点になっていて、一時保育「すまいる」、自主保育「たけのこ」、親子クラブなど、子供と大人、子育て世代と高齢者世代が様々な形でコミュニケーションがとれる施設となっています。また2024年に開園した「なぎっ子こども園」は、保育園と幼稚園計3園を統合した幼保連携型認定こども園で、0歳児から5歳児までが自然な形で交流しています。
――奈義町は「自然とアートのまち」としてもPRされていますが、自然やアートの存在は移住者が増えていることにも関係があるのでしょうか。
子育て支援や教育以外にも、生活に潤いをもたらす自然やアートは住む上で大きな魅力になり、それは若い人も高齢者も同様です。さらにこうした魅力は、町への愛着や誇りを培うことにもつながるので、町としても力を入れています。
そのため都市部との差が少しでも縮まるように、本物のアートに触れる機会を作っているほか、国際交流も積極的に行っています。奈義町にはフランス、アメリカ、インド、韓国からの国際交流員がおり、料理や映画など、楽しみながら外国文化を理解する様々なイベントを開催しています。
――奈義町には世界的な建築家・磯崎新氏が設計した「奈義町現代美術館」もありますよね。
年間来場者数が3万人を越える奈義現代美術館は、アーティストの作品展やイベントも多く、奈義町のアートを象徴する代表的な施設です。
一方で、文化センターはメインの利用者が町民であり、町民が主体的に利用することで満足度が向上する活動を推進していくことが重要です。文化センターは、町民が生活の中で楽しみを見出せる時間と空間を提供できる場所でありたいと思っています。
――奈義町は文化活動も子育て支援も、町民自らが積極的に参加しているのが特徴ですね。
そのためには町民の様々なニーズや意見を、直接聞く機会を設けることが大切です。
例えば奈義町では、子供たちにもまちづくりに積極的に参加してもらうために、小学生が議場で意見を述べる「こども議会」を開催しています。実際2024年には、こども議会で提案された意見を基に環境美化に取り組む「奈義町みんなでつくる美しいまち条例」を制定しました。
これまでは高校卒業後に町から離れる人も多かったですが、こうした体験から町制に関心を持って町に残る人や、一度離れても子育てのために奈義町へ帰ってきてくれる人も出てくるかもしれません。魅力あるまちづくりを推進し、町に愛着を持ってくれる人を育てることが、これからの町の発展につながると考えています。
――町民が主役となって利用する奈義町文化センターのあり方は、地方における文化施設の一つのモデルになるかもしれませんね。本日は貴重なお話をありがとうございました。

取材日:2025年6月
#奈義町文化センター #奈義町 #コトブキシーティング
関連リンク
奈義町 WEBサイト