年に一度開かれている「世界劇場会議国際フォーラム」は、劇場の専門家が集まり熱い議論を交わす貴重な機会です。今年は、長久手市にある
長久手市文化の家で、2024年2月28日から2日間にわたって開催されました。
2024年のテーマ「劇場100年時代は来るのか ~ハードとソフトの相関関係~」

人生100年時代と言われる昨今、公共劇場は100年持続する劇場を目指すべきなのか。また、100年生きる人々に心のオアシスとしてあり続けるべきなのか。ユニークな活動を続けて25周年を迎える長久手市文化の家の活動をハードとソフトの観点から徹底的に検証したうえで、他都市の事例を通して考え、実践者、研究者等が、今後の劇場のあり方を語り合う。
開会に先立って舞台で繰り広げられたのは、音楽とダンス、朗読によるウェルカムパフォーマンスです。パフォーマーは、長久手市文化の家創造スタッフ(以下、創造スタッフ)と呼ばれる専属アーティストのみなさん。
スーツ姿の参加者が集まりビジネスの雰囲気が漂っていた会場が一変、あっという間にアーティスティックな空気に包まれました。彼らの素晴らしいパフォーマンスに、劇場ならではの非日常空間というシチュエーションが合わさり、「なにかステキなことが起こりそう」という期待に胸が膨らみます。劇場のことをとことん考える2日間が始まりました。
開会のご挨拶は、長久手市長の佐藤有美氏とNPO法人世界劇場会議名古屋の理事長を務める下斗米隆氏です。

長久手市長 佐藤有美氏
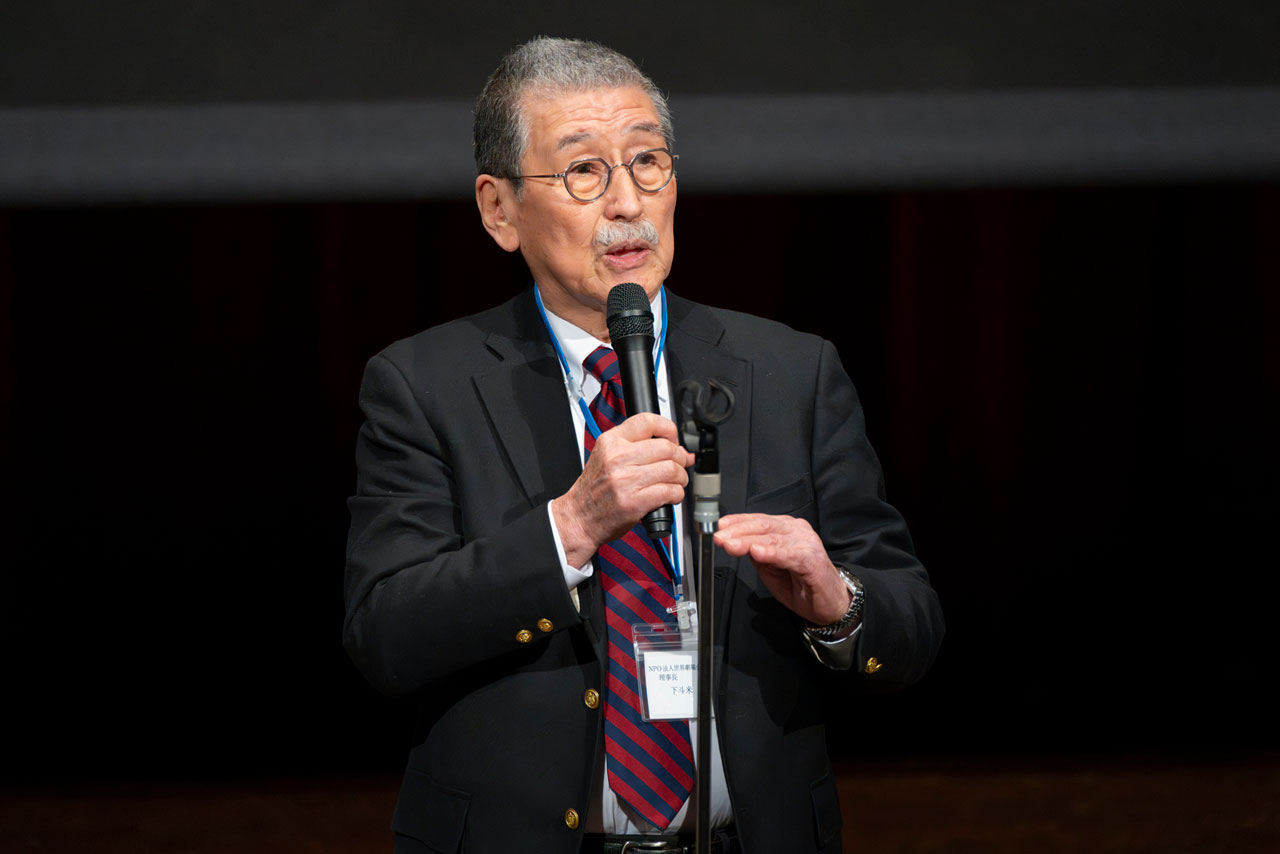
NPO法人世界劇場会議名古屋 理事長 下斗米隆氏
長久手市は、日本で最も平均年齢の若い市。市内には4校の大学がキャンパスを構えています。そのうちの一つ、愛知県立芸術大学は卒業後もこの土地に残る学生が多く、人口の1%が芸術家という芸術のまちだそうです。
そんな長久手市にある今回の会場「長久手市文化の家(以下、文化の家)」は、1998年にオープンしました。舞台公演から式典、集会まで幅広く対応できる「森のホール」「風のホール」「光のホール」という三つのホールと、実習・練習機能や情報・交流機能を備えた芸術文化空間「アートリビング」からなる総合文化施設です。
専門職員と一般行政職員が協働してさまざまな取り組みを行っており、普段から多くの市民で賑わっています。

ボランティアやアーティストとともに創る劇場


1日目は「長久手市文化の家徹底解剖」と題し、ソフトとハードの両面から文化の家についてアプローチしました。進行は、館長である生田創氏です。
年間100本もの自主事業を行い、年間の来場者数は40万人を超えるという文化の家。「市民にとって身近な存在でありつづけたい」という志のもと、日々運営しています。
前半はソフトの部。多様なプログラムを長続きさせるには、さまざまな人の快い協力が必要不可欠です。
稼働率の高い施設を支えているのが、ボランティアスタッフ「フレンズ」の方々です。公演時にはチケットのもぎりや会場内の案内、プログラムの配布など、あらゆるサポートを行っています。「フレンズさんがいなければ公演は成り立たない」と語るのは長久手市文化の家 事業係長の黒瀬さん。30名以上のスタッフをまとめるフレンズ会長の水野さんは「フレンズは研修制度も充実しており、色んな経験を経て仲間ができることが、スタッフの何よりの喜び」と語ります。

長久手市文化の家 事業係長 黒瀬雅直氏

長久手市文化の家 フレンズ会長 水野美々子氏
館内にいくつもの作品が飾られている針金造形作家の橋さんは、元創造スタッフの一人。「お客様と直接触れ合えることが何よりも楽しい。館内の装飾は、いつもの作品とはまた違う創作活動。貴重な経験をさせてもらっています。」と笑顔で話します。同じく元創造スタッフのサックス奏者、石川さんは「施設を飛び出して学校や福祉施設、屋外での演奏も積極的に行っている。アーティストとしての視野が広がった。」と充実した表情で語ります。
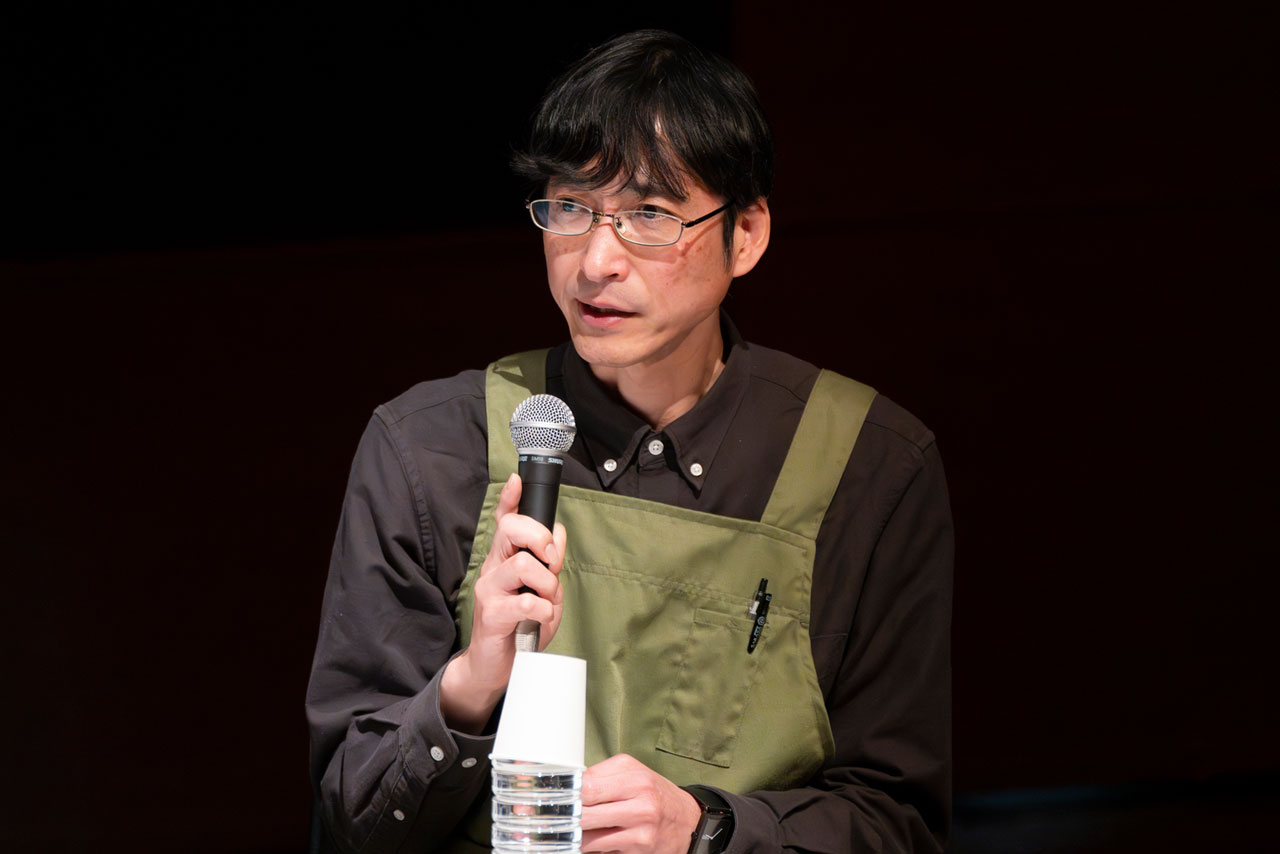
長久手市文化の家 フランチャイズアーティスト 橋寛憲氏

長久手市文化の家 元創造スタッフ 石川貴憲氏
お二人のような創造スタッフの卒業生のなかには、現在も長久手市に住み、さまざまな形で文化の家とのコラボレーションを行っているアーティストが多いそう。このような芸術家が活動しやすいまちというのは、全国を探してもまだ少ないかもしれませんね。

橋寛憲氏による針金アート作品
さまざまな演目を実現するオリジナルのホール設備
1日目の後半は、ハードの部。会場となった森のホールについて、舞台照明・舞台機構・座席、それぞれのメーカー担当者による説明です。

(左から)森平舞台機構(株)松江豊氏、コトブキシーティング(株)丸山洋史、東芝ライテック(株)本堂武志氏、長久手文化の家 籾山勝人氏
森のホールは、演目に合わせたホール空間をつくれるよう、舞台も客席も可変する仕掛けが多くあります。
その一つが、舞台と客席の間にあり、舞台を額縁のように区切るプロセニアム・アーチ。前後に動くようになっており、舞台の大きさを変えられることで演目に応じたスペースが確保できます。
さらに演目の幅を広げるのが、客席の転換です。馬蹄形の客席は、馬蹄形をなぞるように設けられた横通路の内側が転換します。その転換方法が驚異的なのです。イスが設置された床が上昇し、前転するように180度回転し、裏面のイスの無い床になるという仕組み。ものの数分で、あっという間に客席だった場所が平土間空間に転換しました。

客席から平土間へ、舞台転換の様子
舞台と客席の転換に合わせて、照明も変えなければなりません。通常は舞台という決められたエリア内での調整になりますが、舞台と客席の広さと位置が変わるため都度最適に調整できるよう、フロントライトを昇降式にするなど、普通のホールにはないさまざまな仕掛けが施されていました。
そして座席にずらりと並ぶイスは、コトブキシーティングが施設の竣工当時に納品した森のホールのための特注イスです。客席の馬蹄配置を模したように丸くトリミングされた背板は、お客様の背中をそっと抱き抱えるようなカーブをつけています。表面からビスなどの部品が見えないよう配慮された意匠は、まるで建築の一部分のような雰囲気。カバ材の木部とスエード調の張地が、重厚感を一層高めています。納品以来、大規模なメンテナンスもしていませんが、大きなトラブルもなくお客様からの評判も上々とのこと。非常に嬉しい限りです。

長久手文化の家 森のホールのための特注イス
1日目の締めくくりには、前方の客席を平土間に転換し、来場者による懇親会が行われました。
取材日:2024年2月28日
取材:広報企画部 M.A
#世界劇場会議国際フォーラム #長久手市文化の家 #長久手市 #NPO法人世界劇場会議名古屋 #森のホール #風のホール #光のホール #アートリビング #劇場 #コトブキシーティング
【レポート】「劇場」をとことん考える!世界劇場会議国際フォーラム 2024 in長久手 レポート(後編)
関連リンク
世界劇場会議国際フォーラム WEBサイト
長久手市 文化の家 WEBサイト